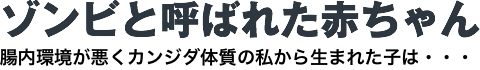「牛乳が体に良くない」という話はいろいろなところで見かけます。
それに対して、「牛乳は完全栄養食」という意見もあります。
本当のところはどうなのでしょう?
牛乳の成分から乳牛のエサ、飼育環境などを考慮して、牛乳が体に良くない10個の理由を説明します。
牛乳が体に良くない理由

1、カルシウムの吸収を阻害し、骨粗鬆症のリスクを上げる
牛乳といえば「カルシウムが豊富で、強い骨や歯を作る」イメージがありますが、実際カルシウムは豊富でも、飲めば飲むほど骨粗鬆症のリスクを上げてしまうようです。
牛乳には1リットル中1200ミリグラムのカルシウムが入っていますが、カルシウムが体内で代謝されるために必要なマグネシウムがほとんど入っていないため、強い骨や歯を作るということはないようです。
そして牛乳に含まれるリンというミネラルが、腸の中でカルシウムと結合してしまい、カルシウムの吸収を阻害します。
さらに、牛乳のたんぱく質は消化器内で分解されてアミノ酸になります。
体内でのアミノ酸の量が過剰になると血液が酸性に傾き、それを中和するために、体は骨の中のカルシウムを溶かして血液中に送り込む作業をします。
これは『脱灰(だっかい)』といい、骨粗鬆症の初期段階です。
2、飽和脂肪酸が血液循環を悪くする
牛乳の脂肪の主体、飽和脂肪酸が血液の粘度を上げ、血液循環を悪くし脳梗塞や心筋梗塞のリスクを上げます。
さらに、コップ1杯の牛乳には最大24mgのコレステロールが含まれます。
牛乳を飲むことで血中のコレステロールや中性脂肪を増やし、糖尿病や肥満、高脂血症などの生活習慣病にかかりやすくなるリスクもあります。
3、ホルモン
牛乳のホルモンの問題は成長ホルモン・女性ホルモンの2種類に分けられます。
成長ホルモン
rBGHホルモンという米モンサント社が開発した成長促進のためのホルモンが、乳牛と食肉用の牛に投与されています。
rBGHホルモンは発がん性の疑いがあり、EUではヨーロッパ内での使用、輸入共に認可されていません。
日本国内でも成長ホルモンの使用は認められていません。
ただし輸入の乳製品には認められています。
女性ホルモン
出産経験のある方なら分かると思いますが、妊娠中、母乳はほとんど出ません。
そして授乳が終わると母乳の生産も止まり、出なくなります。
乳牛は牛乳を搾り取られるために、まず妊娠→出産します。
産後、赤ちゃん牛は引き離され、人工乳で飼育されます。(オスの子牛はその後すぐに食肉になり、メスの子牛は乳牛として1歳半前後で人工的に妊娠させられます。)
お母さん牛は赤ちゃんにあげるはずだった母乳を、牛乳として人間に(文字通り)搾取されます。
母乳が絞られている限りお母さん牛の体は母乳を生産しますが、それもだんだん生産量が減ってきます。
そのため、お母さん牛はまた人工的に妊娠させられます。
そして、妊娠中も牛乳を絞られます。
妊娠中は卵胞ホルモン(エストロゲン)や黄体ホルモン(プロゲステロン)が多量に分泌されるため、妊娠中に搾乳された牛乳中にもこれらの女性ホルモンが多量に混入します。
この女性ホルモンが人間に与える影響として、
・リンパ球のTh1という細胞性免疫能が低下するためアレルギー体質になりやすい
・女子の初潮が早まる
・発達過程にある小児の免疫・神経・生殖(とくに男児)に影響
などがあります。
そして、5~6年常に妊娠させられ牛乳を搾り取られたお母さん牛は、食肉工場に送られます。

4、抗生物質
乳牛も肉牛も狭い牛舎で糞尿にまみれて飼育されているため、健康的な生活を送れません。
病気になる牛も多いため、それを予防するために抗生物質が投与されます。
投与された抗生物質は、牛の体内で消えることはなく牛乳や牛肉に混入しています。
また乳牛に限って言うと、投与される成長ホルモンに母乳の生産量を上げる作用もあり、乳腺炎になる乳牛が多いそうです。
その予防にも抗生物質が使われています。
5、発がん性
まず一つは、牛乳の女性ホルモンが乳がん、子宮がん、卵巣がん、前立腺がんなどを引き起こす可能性。
次に、カビ毒であるアフラトキシンに汚染されたトウモロコシ飼料を食べる乳牛からの牛乳にも、アフラトキシンが混入し、アフラトキシンは肝臓を主な標的として毒性や発がん性の可能性があります。
日本の酪農は飼料としてアフラトキシン汚染の代表とも言える米国産トウモロコシに依存しています。
実際、厚労省は2001年12月から2002年1月にかけて全国的に流通している牛乳を検査したところ、調査対象のほとんどすべての牛乳からアフラトキシンM1が検出されたそうです。
ただ、汚染レベルは国際基準の0.2~5.6%の範囲内だったのでそのまま流通されたようですが。
6、乳糖不耐症
乳糖不耐症とは、乳糖(ラクトース)の消化酵素のラクターゼが消化できないことで、消化器に生じる諸症状のことです。
歴史的にもともと牛乳を飲んでいなかった日本人は、乳糖不耐症が多いと言われますが、乳糖不耐症という診断を受けなくても全員が実は乳糖不耐症、という意見もあります。
牛乳は、牛の赤ちゃんの飲み物であって、人間が飲むものではないということなのかもしれません。
7、ダイオキシン
発ガン性,催奇性,免疫毒性などの可能性が強いダイオキシン。
日本でのダイオキシンの問題は、廃棄物焼却に関心が集中したことが強く印象に残りますが、問題視すべきダイオキシン類に汚染されている程度が相対的に高いのは,肉類,乳製品,魚類といった脂質含量の高い動物性食品である、ということです。
8、ニキビの原因になる
牛乳を飲むと、男性ホルモン(テストステロン)が過剰になり、男女を問わず皮脂の分泌量が増え、硬くなった角質と共に毛穴を塞いでしまいニキビができやすくなります。
さらに、動物性脂肪は皮脂腺を刺激する作用があり、さらに毛穴を詰まらせます。
9、男性のパーキンソン病発症率を上げる可能性
筋肉がこわばり動作が遅くなるなどの症状が現れ、寝たきりになるケースもあるパーキンソン病。
ハリウッドの映画俳優マイケル・J・フォックスさんが発症したことで有名です。
米ハーバード大学公衆衛生大学院の研究で、乳製品を毎日3人分以上を摂取した人たちは、1人分以下の摂取の人たちと比べ、パーキンソン病の発症リスクが34%高かったことが示されています。
これは、牛乳に含まれる抗生物質・農薬・ホルモンなどが腸内バランスに与える影響が原因である可能性が指摘されています。
10、異なる種の動物の乳を飲むということ
自然界で異種の生き物の母乳を飲むのは人間だけなんだそうです。
YouTubeで犬のおっぱいを飲む子猫を見たことがあるような気がしますが、あれは特別なんでしょう。
繰り返しになりますが、人間の母乳は人間の赤ちゃんに必要な成分でできていて、牛の母乳も牛の赤ちゃんに必要な成分でできているため、人間がそれを飲むというのは不自然なこと。
不自然なことを続けていると、歪みが生じてくるの当然です。
たとえ人工的にホルモンを投与されていない野生の牧草だけを食べている牛の牛乳だったとしても、体の大きさも全然違う人間には合わないということです。

まとめ
乳牛のエサ、飼育携帯から牛乳の成分まで、どれを取っても牛乳が体にいいとは思えない結果でした。
コーヒーや紅茶に少し入れる、たまに乳製品を食べる程度なら問題はないと思いますが、毎日ガブガブ飲むことは控えたほうが良さそうです。
特に成長期の子どもや妊娠中、授乳中のお母さんには避けてもらいたい食品です。
個人的には、生まれたばかりの子牛と産後1日ほどで引き離され、ひたすら牛乳を搾り取られるお母さん牛の牛乳には、その悲しい気持ちがいっぱい詰まっているような気がしてしまい、牛乳を飲む気になれないです。
これは私の勝手な想像で、科学的には証明されていないことですが…
牛乳を使う料理はココナッツミルクで代用!
「病気にならない生き方」新谷弘実(著)には、以下のように述べられています。
市販の牛乳は「錆びた脂」ともいえる。
ホモゲナイズすることにより、生乳に含まれていた乳脂肪は酸素と結びつき、「過酸化脂質」に変化してしまいます。
超高温にされることによって、過酸化脂質の量はさらに増加します。