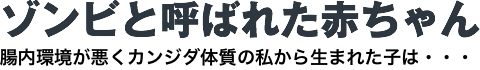春になると、針葉樹の枝の先から新芽が出てきます。
この新芽は栄養価が高く、食べられます。
この記事では、針葉樹の新芽の採取方法、時期、摂取方法、効能について説明します。
針葉樹とは?
針葉樹とは、葉が針のように細長い樹木のことです。
- 松
- 杉
- もみ
- ヒノキ
- トウヒ
- あすなろ
などがあります。
秋や冬になっても葉が落ちることなく一年中緑の葉を茂らせているため、常緑樹(エバーグリーン)とも呼ばれます。
日本には松、杉、ヒノキ、あすなろなどが主に自生していますが、私の住むカナダ西海岸では、松、杉、もみ、トウヒ、ツガ(栂)が多く自生しています。
クリスマスツリーの印象が強いもみの木は英語でファー(fir)、見た目はもみに似ているトウヒはスプルース(spruce)と呼んでおり、その新芽はファーティップ(fir tips)、スプルースティップ(spruce tips)と呼びます。

イチイの実
ほとんどの針葉樹の新芽は食べられるのですが、長野や日本海側の地域で多く見られるイチイという針葉樹は例外で、毒性があります。生け垣にも使われる木です。
杉の葉も食用には向いていません。
食用に向いている針葉樹の新芽は、もみ、トウヒ、ツガです。
日本でも寒い地域には、食用に適した新芽をつける針葉樹が自生しています。
新芽の採取
野草を採取する際、「100mルール」という大きい幹線道路などからは最低100メートル離れた場所で採取しましょうという決まり(?)があります。
排気ガスなどの汚染の影響を受けている野草はできるだけ避けたいからです。

針葉樹の新芽は、春になると枝の先から出てきます。
上の写真はもみの木の新芽で、初めは茶色く薄い皮に包まれています。
成長してくると皮がはがれ落ちます。
この段階の新芽が採取に適しています。

既存の葉は硬いのに対し、新芽は柔らかいです。
新芽が摘まれた場所は今年は成長できませんが、来年の春になったら新しい芽が生えてきます。
採取した新芽は、この場ですぐ食べることもできます。
柑橘系のフレーバーと樹脂のフレーバーが混ざったような、なんとも爽やかな味がします。

新芽の摂取方法
針葉樹の新芽は、採ってすぐにそのまま食べられます。
その他の摂取方法は、
- インフューズドウォーター(新芽を飲み水に浸す)
- お茶
- 塩漬け
- はちみつ漬け
- アップルサイダービネガー漬け
- サラダドレッシング
- サルサ
- ワカモーレ
- フムス
- スムージー
- シロップ
- スープ
- 肉・魚料理
などなど、ハーブと同じように使用できます。

針葉樹の新芽は、乾燥させて保存できます。
春に1年分採取して、冬のビタミンC摂取源にしたいですね。
新芽の効能
針葉樹の葉は地面に落ちて分解されることで、森の土に栄養を与えます。
新芽に含まれる栄養素は以下の通りです。
- ビタミンC
- ビタミンE
- ビタミンK
- ビタミンB1
- ビタミンB2
- ビタミンB6
- カロテノイド
- カリウム
- マグネシウム
- クロロフィル
特にビタミンCが豊富なことが特徴で、レモンの7倍含まれるそうです。
針葉樹の新芽のビタミンCは様々な微量栄養素と結合することで、体が使用しやすい形態のビタミンCになっています。
市販のビタミンCサプリメントは通常アスコルビン酸単体の形態なため、体が使用する際に体が貯蔵していた微量栄養素を消耗します。
この理由のため、ビタミンCはサプリメントからよりも食品から摂取することが推奨されます。

新芽を数時間水に浸したインフューズドウォーターは、水溶性の栄養素が水に溶け出します。
とても爽やかな味でクセになります。
ビタミンC以外にも抗酸化物質を豊富に含む針葉樹の新芽は、以下のような効能があります。
- 心血管疾患のリスクを減らす
- コレステロールの調整
- 血管壁の炎症を軽減
- 代謝の調整
- 循環器系の改善
- 損傷した組織の回復を促進
- フリーラジカルの中和
- アレルギーの改善
- 発がん性物質の形成を軽減
- 肌の若返り
- デトックス
よほど若い木ではない限り、何年もそこに立っていてその地域の気候の変化や波動の変化を見てきている針葉樹からの新芽は、その地域に住む人がその時期に必要な栄養素を必要な量だけ備えていると思います。
感謝の気持ちでありがたく新芽を頂けば、さらなる相乗効果も期待できると思います。
まとめ

針葉樹の新芽の採取、摂取方法、効能について説明しました。
針葉樹は寒い地域に生える木なので日本でも暖かい地域にお住いの方はあまり見かけないかもしれませんが、もし4月後半〜5月前半頃に標高の高いところにお出かけする機会がありましたら、ぜひ探してみてください。