ビタミンB12と鉄分の不足が原因で貧血になる人が増えています。
貧血というと鉄分の不足が原因と思いますが、ビタミンB12の不足も原因になっています。
この貧血には腸内環境が深く関係していて、ただサプリメントや食事でビタミンB12を摂取するだけでは解決は難しいようです。
放置していしまうと他の深刻な病気につながる可能性もあり、早めに対処しておきたい問題です。
この記事では、ビタミンB12の役割、欠乏した際の症状、不足する理由、欠乏を改善する方法について説明しています。
ビタミンB12とは?

ビタミンB12は赤血球の形成やタンパク質の合成、神経細胞の修復などを行っている栄養素です。
ビタミンB12は体内にある腸内細菌よって作られており、肝臓に蓄えられているため、本来は欠乏しにくい栄養素です。
ベジタリアンなど極端な偏食傾向のある人や、胃や腸を手術で切除した方は不足する可能性があるので、注意が必要です。
これは出産時に大量に出血するということもありますが、生まれた赤ちゃんは腸が完成するまで鉄分を吸収できないため、お腹の中でお母さんにもらった鉄分を貯蔵して使っていきます。
ビタミンB12が不足すると鉄分も不足するので、気をつけておきましょう。
ビタミンB12欠乏の症状
●悪性貧血
●動悸
●息切れ
●倦怠感
●疲労
●めまい・立ちくらみ
●食欲不振
●うつ
●手足のしびれ
●消化器系の問題(下痢、吐き気など)
●ブレインフォグ
ビタミンB12不足になる原因
ビタミンB12は、食べ物からの摂取で肝臓に蓄えられ、さらに腸内細菌によっても生産されます。
1、食事から十分に摂取できていない
牡蠣などの魚介類やレバーといった動物性食品に多く含まれており、果物や野菜など植物性食品にはほとんど含まれていない上に、含まれていても植物性のビタミンB12は吸収されにくい特徴があるようです。
1日の摂取推奨量は、成人男性・女性ともに2.4μgとなっています。
そのためベジタリアンや肉嫌い、魚介類嫌いの人は不足しやすい傾向にあります。
2、腸内環境の悪化で吸収できていない
ビタミンB12を十分に摂取しても、腸内環境が悪い場合、ビタミンB12が吸収されず欠乏の状態は改善されません。
ビタミンB12吸収不良の原因
1、低胃酸
胃酸に十分なベタインとペプシンという消化を助ける酵素が不足していると、ビタミンB12と結合している動物性たんぱく質の消化が困難になります。
ピロリ菌感染などで、萎縮性胃炎または低塩酸症を患っている人は注意が必要です。
胃酸を抑制する薬を服用している人も気をつけてください。
2、外分泌性膵機能不全
十分な膵臓酵素が生産されていない状態では、ビタミンB12は小腸を通過して吸収されます。
3、腸内細菌異常増殖症候群(SIBO)
腸内細菌異常増殖症候群とは、腸内に細菌が異常増殖してしまう症状です。
過敏性腸症候群(IBS)と診断される中の約80%の人が腸内細菌異常増殖症候群を併発していると言われています。
腸内細菌異常増殖症候群で、腸内に悪玉菌が増殖している状態だと、ビタミンB12は体内に吸収される前に消費される可能性があります。
これは細菌だけではなく、特定の寄生虫でも同じ問題が起きます。
4、食べ物の丸飲み
ビタミンB12が吸収されるには、食べ物に含まれるたんぱく質に結合するか、唾液中のハプトコリンというたんぱく質に結合する必要があります。
よく噛んで唾液を分泌させることで、よりビタミンB12を吸収しやすくなります。
3、MTHFR遺伝子の突然変異
MTHFR??
と思ってしまいますが、Methyl-tetrahydrofolate reductase(メチルテトラヒドロ葉酸レダクターゼ)という、 体のあらゆる細胞のメチル化を担う酵素ということです。
メチル化とは、炭素1つと水素3つから成る. 他の物質にメチル基が結合することがメチル化らしいのですが、
わかりにくいですね。
ビタミンB12は摂取された後に体内でメチル化して使用可能な状態にしてあげないと、必要な組織に吸収されず、無駄になってしまうということのようです。
MTHFR遺伝子に突然変異があると、酵素活性が低下し、ビタミンB12の吸収に影響が出るようです。
腸内細菌のバランスを整え、十分なビタミンB12を摂取しても症状が改善されない場合、このMTHFR遺伝子が変異しているかどうかを調べる検査をしてみてもいいかもしれません。
ビタミンB12欠乏を改善する方法
腸内環境の改善
腸内環境が悪い状態だと、ビタミンB12を摂取しても吸収されず無駄にしてしまうだけです。
まずは腸内環境を改善させることが大切です。
腸内環境の改善に食生活の改善は不可欠です。
カンジダダイエットは、腸内のカンジダ菌除菌を目的にした食事制限で、腸内環境の改善に効果があります。

プロバイオティクス摂取
カンジダダイエットを始めると同時に、発酵食品やサプリメントからプロバイオティクスを摂取します。


ビタミンB12摂取
1日の摂取推奨量は、成人男性・女性ともに2.4μgとなっています。

ビタミンB12が豊富な食べ物
牛肉
ラム
レバー
ターキー
卵
しじみ
海苔
あさり
ハマグリ
サーモン
ニシン
サバ
イワシ
マグロ
サプリメント
ビタミンB12のサプリメントは、通常カプセルの形態になっています。
腸内細菌異常増殖症候群(SIBO)、過敏性腸症候群(IBS)などの場合、カプセルで摂取するよりもはるかに吸収の効果が高い、液体のビタミンB12を舌下ドロップで摂取します。
悪性貧血や神経障害などの深刻な症状が出ている場合は、医療機関で注射してもらう必要があります。
まとめ
吸収のされ方がとてもややこしいビタミンB12ですが、まとめるとこういうことです。
●ビタミンB12が不足すると鉄分も不足する
●ビタミンB12は肉や魚介類から摂取するか、腸内細菌に作ってもらう
●ビタミンB12は摂取しても腸内環境が悪かったら吸収されない
●胃液に含まれる胃酸の分泌、消化酵素の分泌がビタミンB12の吸収に関わっている
●腸内環境を改善し、ビタミンB12も摂取しているのに症状が改善されない場合は、MTHFR遺伝子の検査をする
●サプリメントは症状によって、カプセル、液体、医療機関での注射を選ぶ
胃酸や消化酵素の分泌は加齢によって低下する傾向にあるようです。
アラフォーでカンジダ症の私もたまに立ちくらみすることがあるので、気をつけなくてはと思っています。
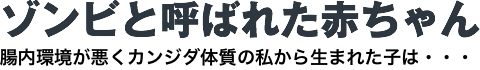




・貧血の人
・カンジダ症の人
・腸内細菌異常増殖症候群(SIBO)の人
・過敏性腸症候群(IBS)の人
・外分泌性膵機能不全
・妊娠中の人